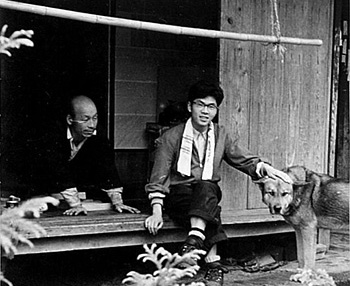| Tweet [テーマページ目次] [ダム便覧] [Home] |
|---|
ダムインタビュー(67)
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 関連する 「このごろ」「テーマページ」】
(ダムインタビュー) [テ] ダムインタビュー(1)萩原雅紀さんに聞く「宮ヶ瀬ダムのインパクトがすべての始まり」 [テ] ダムインタビュー(2)宮島咲さんに聞く「ダム好き仲間とOFF会に行くのが楽しい」 [テ] ダムインタビュー(4)川崎秀明さんに聞く「ダムファンがいるからプロもやる気になる」 [テ] ダムインタビュー(5)高田悦久さんに聞く「ダム現場では行動することが一番大事だ」 [テ] ダムインタビュー(7)takaneさんに聞く「ダムの管理をしている人がブログを立ち上げてくれたら、僕読みますよ」 [テ] ダムインタビュー(6)さんちゃんに聞く「ベストショットは川口ダムの夜景です」 [テ] ダムインタビュー(8)土木写真家・西山芳一さんに聞く「いい写真は努力や熱意が伝わってくる」 [テ] ダムインタビュー(10)水資源機構・金山明広さんに聞く「地元、ダムマニア、ダム管理事務所がコラボレーションできれば」 [テ] ダムインタビュー(11)古賀河川図書館館長・古賀邦雄さんに聞く「将来は1万冊を目標にしようという気持ちでいます」 [テ] ダムインタビュー(12)中村靖治さんに聞く「ダムづくりの基本は、""使いやすいダム""を設計するということです」 [テ] ダムインタビュー(13)江守敦史さんに聞く「ダムについて何時間も語れる萩原さん。彼と本質を突き詰めたからこそ、面白い本になりました」 [テ] ダムインタビュー(14)藤野浩一さんに聞く「欧米では水力を含む再生可能エネルギーの開発に重点を置いています」 [テ] ダムインタビュー(15)安河内孝さんに聞く「”碎啄同時(そったくどうじ)”という言葉があります。モノづくりの技術の継承は、教える側と教わる側の力が寄り添ってこなければ、うまくいかない」 [テ] ダムインタビュー(16)石川順さんに聞く「ふと閃いたのがダムだったんです。」 [テ] ダムインタビュー(17)杉野健一さんに聞く「経験を重ねるというのはダム技術者にとって大事な財産」 [テ] ダムインタビュー(3)灰エースさんに聞く「ダムだから悪いという書き方はおかしい」 [テ] ダムインタビュー(18)だいさんに聞く「ダムを見るいちばんのポイントは機能美だと思っています」 [テ] ダムインタビュー(19)琉さんに聞く「時々 ""ダム王子"" とか呼ばれちゃってますけど」 [テ] ダムインタビュー(20)西田博さんに聞く「一部分の経験しかない人が増えることで、ダム技術の継承が心配される」 [テ] ダムインタビュー(21)緒方英樹さんに聞く「“土木リテラシー”の必要性を強く感じています」 [テ] ダムインタビュー(22)吉越洋さんに聞く「電力のベストミックスといって、火力、水力、原子力などの最適な組み合わせを考えて、計画をたてています」 [テ] ダムインタビュー(23)竹林征三さんに聞く「ダムによらない治水と言うが、堤防を強化して首都圏の大都市を守れるのか」 [テ] ダムインタビュー(24)高橋裕先生に聞く「公共事業を軽んずる国の将来が危ない」 [テ] ダムインタビュー(25)竹林征三さんに聞く(その2)「風土との調和・美の法則を追求して構築したのが『風土工学理論』です」 [テ] ダムインタビュー(26)竹村公太郎さんに聞く「未来を見通したインフラ整備が大事で、ダムの役目はまだまだ大きいですよ」 [テ] ダムインタビュー(27)虫明功臣先生に聞く「八ッ場ダムは利根川の治水・利水上必要不可欠」 [テ] ダムインタビュー(28)水野光章さんに聞く「水と安全はタダといった安易な考えではいけないと、あらためてそう思います」 [テ] ダムインタビュー(29)萃香さんに聞く「ダムの魅力を引き出せるような写真を撮って公開していきたい」 [テ] ダムインタビュー(9)Dam masterさんに聞く「機能と造形と自然の組み合わせが面白い」 [テ] ダムインタビュー(30)樋口明彦先生に聞く「ひっそりと自然の中に佇むようなダムが美しい、とスペインの名もないダムを見て気づいた」 [テ] ダムインタビュー(31)宮村 忠先生に聞く「これからは‘線’ではなく‘点’で勝負すべきだ」 [テ] ダムインタビュー(32)土屋信行さんに聞く「きちんとやるべきことと、そうでないことの本当の仕分けが今こそ必要ではないか」 [テ] ダムインタビュー(33)沖大幹先生に聞く「ダムは造りすぎではなく最低限の備えが出来た段階だ」 [テ] ダムインタビュー(34)阪田憲次先生に聞く「技術者には""想定外を想定する想像力""が求められている」 [テ] ダムインタビュー(35)谷 茂さんに聞く「これからは少しゆっくりと環境に負荷を与えないかたちでダムを造る方法もあるのではないか」 [テ] ダムインタビュー(36)大藪勝美さんに聞く「インフラの重要性をもっと多くの人に知ってもらいたい」 [テ] ダムインタビュー(37)武田元秀さんに聞く「四十年来の思いが叶い、『ダムと鉄道』にまつわる話を出版することができました」 [テ] ダムインタビュー(38)山内 彪さんに聞く「若い人は、ダムを糧として立派な総合技術者として育っていって欲しい」 [テ] ダムインタビュー(39)角哲也先生に聞く「ダムのアセットマネジメントの話をするときに何か目標がいる、千年ではどうかと」 [テ] ダムインタビュー(40)唐澤一寛さんに聞く「人にものを頼もうとする時は、こちらも誠意をもって付き合わなければいけない」 [テ] ダムインタビュー(41)糸林芳彦さんに聞く「今は新規のダム計画がなくとも、ダム技術は常に磨いておくべき。いずれ時代の要請に応える日が来るから。」 [テ] ダムインタビュー(42)今村瑞穂さんに聞く「ダム操作の定式化と現場適用性の向上は車の両輪」 [テ] ダムインタビュー(43)本庄正史さんに聞く「ダムの海外展開は、現地社会に貢献するという、貢献がキーワードだと思います」 [テ] ダムインタビュー(44)石田哲也先生に聞く「何か起きたときのリスクのあるシナリオをきちんと一般の人に伝えていかないと」 [テ] ダムインタビュー(45)古川勝三さんに聞く「今こそ、公に尽くす人間が尊敬される国づくり=教育が求められている」 [テ] ダムインタビュー(46)入江洋樹さんに聞く「水を大切にするという日本人の心の原点を守り、継承していけば1000年先もダムは残っていく」 [テ] ダムインタビュー(47)島谷幸宏先生に聞く「設計をする時に環境設計と治水設計を一体的にすることが一番重要なのです」 [テ] ダムインタビュー(48)吉津洋一さんに聞く「先人から受け継いだ素晴らしい‘くろよん’をしっかり守り、引き継いでいきたい」 [テ] ダムインタビュー(49)足立紀尚先生に聞く「ダムの基礎の大規模岩盤試験を実施したのは黒部ダムが最初でした」 [テ] ダムインタビュー(50)山口温朗さんに聞く「徳山ダムの仕事はまさに地図にも、私の記憶にも残る仕事となりました」 [テ] ダムインタビュー(51)安部塁さんに聞く「新しい情報を得たらレポートにまとめてダム便覧に寄稿しています」 [テ] ダムインタビュー(52)長瀧重義先生に聞く「土木技術は地球の医学、土木技術者は地球の医者である」 [テ] ダムインタビュー(53)大田弘さんに聞く「くろよんは、誇りをもって心がひとつになって、試練を克服した」 [テ] ダムインタビュー(54)大町達夫先生に聞く「ダム技術は、国土強靱化にも大きく寄与できると思います」 [テ] ダムインタビュー(55)廣瀬利雄さんに聞く「なんとしても突破しようと強く想うことが出発点になる」 [テ] ダムインタビュー(56)近藤徹さんに聞く「受け入れる人、反対する人、あらゆる人と話し合うことでダム建設は進められる」 [テ] ダムインタビュー(57)小原好一さんに聞く「ダムから全てを学び、それを経営に活かす」 [テ] ダムインタビュー(58)坂本忠彦さんに聞く「長いダム生活一番の思い出はプレキャスト型枠を提案して標準工法になったこと」 [テ] ダムインタビュー(59)青山俊樹さんに聞く「相手を説得するのではなく、相手がどう考えているのかを聞くことに徹すれば、自然に道は開けてくる」 [テ] ダムインタビュー(60)中川博次先生に聞く「世の中にどれだけ自分が貢献できるかという志が大事」 [テ] ダムインタビュー(61)田代民治さんに聞く「考える要素がたくさんあるのがダム工事の魅力」 [テ] ダムインタビュー(62)ダムマンガ作者・井上よしひささんに聞く「ダム巡りのストーリーを現実に即して描いていきたい」 [テ] ダムインタビュー(63)太田秀樹先生に聞く「実際の現場の山や土がどう動いているのかが知りたい」 [テ] ダムインタビュー(64)工藤睦信さんに聞く「ダム現場の経験は経営にも随分と役立ったと思います」 [テ] ダムインタビュー(65)羽賀翔一さんに聞く「『ダムの日』を通じてダムに興味をもってくれる人が増えたら嬉しい」 [テ] ダムインタビュー(66)神馬シンさんに聞く「Webサイト上ではいろんなダムを紹介する百科事典的な感じにしたい」 [テ] ダムインタビュー(68)星野夕陽さんに聞く「正しい情報を流すと、反応してくれる人がいっぱいいる」 [テ] ダムインタビュー(69)魚本健人さんに聞く「若い人に問題解決のチャンスを与えてあげることが大事」 [テ] ダムインタビュー(70)陣内孝雄さんに聞く「ダムが出来たら首都圏の奥座敷として 訪れる温泉場に再びなって欲しい」 [テ] ダムインタビュー(71)濱口達男さんに聞く「ダムにはまだ可能性があっていろんな利用ができる」 [テ] ダムインタビュー(72)長門 明さんに聞く「ダム技術の伝承は計画的に行わないと、いざ必要となった時に困る」 [テ] ダムインタビュー(73)横塚尚志さんに聞く「治水の中でダムがどんな役割を果たしているか きちんと踏まえないと議論ができない」 [テ] ダムインタビュー(74)岡本政明さんに聞く「ダムの効用を一般の人々に理解頂けるようにしたい」 [テ] ダムインタビュー(75)柴田 功さんに聞く「技術者の理想像は“Cool Head Warm Heart”であれ」 [テ] ダムインタビュー(76)山岸俊之さんに聞く「構造令は,ダム技術と法律の関係を理解するのに大いに役に立ちました」 [テ] ダムインタビュー(77)毛涯卓郎さんに聞く「ダムを造る人達はその地域を最も愛する人達」 [テ] ダムインタビュー(78)橋本德昭氏に聞く「水は土地への従属性が非常に強い,それを利用させていただくという立場にいないと成り立たない」 [テ] ダムインタビュー(79)藤野陽三先生に聞く「無駄と余裕は紙一重,必要な無駄を持つことで,社会として余裕が生まれると思います」 [テ] ダムインタビュー(80)三本木健治さんに聞く「国土が法令を作り,法令が国土を作る -法律職としてのダムとの関わり-」 [テ] ダムインタビュー(81)堀 和夫さんに聞く「問題があれば一人でしまいこまずに,記録を共有してお互いに相談し合う社会になってほしい」 [テ] ダムインタビュー(82)佐藤信秋さんに聞く「国土を守っていくために, 良い資産,景観をしっかり残していくことが大事」 [テ] ダムインタビュー(83)岡村 甫先生に聞く「教育は,人を育てるのではなく,人が育つことを助けることである」 [テ] ダムインタビュー(84)原田讓二さんに聞く「体験して失敗を克復し, 自分の言葉で語れる技術を身につけてほしい」 [テ] ダムインタビュー(85)甲村謙友さんに聞く「技術者も法律をしっかり知らないといけない,専門分野に閉じこもってはいけない」 [テ] ダムインタビュー(86)前田又兵衞さんに聞く「M-Yミキサ開発と社会実装 ~多くの方々に支えられ発想を実現~」 [テ] ダムインタビュー(87)足立敏之氏に聞く「土木の人間は全体のコーディネーターを目指すべき」 [テ] ダムインタビュー(88)門松 武氏に聞く「組織力を育てられる能力は個人の資質にあるから, そこを鍛えないといけない」 [テ] ダムインタビュー(89)佐藤直良氏に聞く「失敗も多かったけどそこから学んだことも多かった」 [テ] ダムインタビュー(90)小池俊雄氏に聞く「夢のようなダム操作をずっと研究してきました」 [テ] ダムインタビュー(91)米谷 敏氏に聞く「土木の仕事の基本は 人との関係性を大事にすること」 [テ] ダムインタビュー(92)渡辺和足氏に聞く「気象の凶暴化に対応して,既設ダムの有効活用, 再開発と合わせて新規ダムの議論も恐れずに」 [テ] ダムインタビュー(92)渡辺和足氏に聞く「気象の凶暴化に対応して,既設ダムの有効活用, 再開発と合わせて新規ダムの議論も恐れずに」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [テーマページ目次] [ダム便覧] [Home] |
|---|